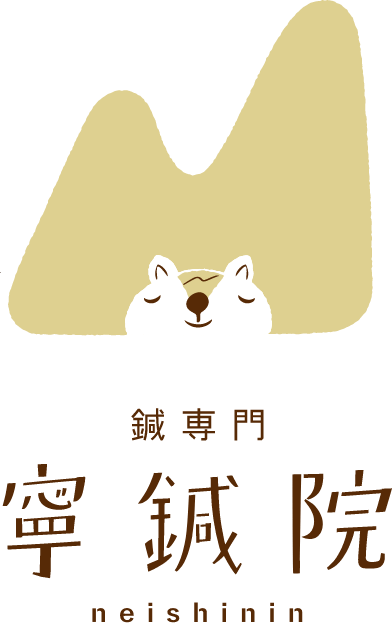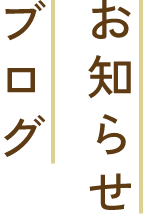2025.10.06
- ブログ
東洋医学に基づく鍼灸を選んだ理由(後編)
前編では、看護師を辞めて鍼灸師を目指した理由について述べさせていただきました。今回の後編では、東洋医学とそれに基づく鍼灸治療を選んだ理由についてご説明させていただきます。
妻にかけられた意外な言葉
さて、予防医学を実践するために看護職を辞し、鍼灸師になると決めたのはよいのですが、妻にはまだ相談していませんでした。
「これは離婚すると言われても仕方ないよな」と悩みながらも妻に自分の気持ちを打ち明けると、驚いたことに快諾してくれました。むしろ、私が鍼灸師になるといつか言い出すのではと思っていたと言われました。
妻は以前から私は看護師よりも鍼灸師に向いていると思っていたそうなのですが、看護師として懸命に働いている姿をみて、あえて伝えなかったとも言われました。
快諾してくれた妻には今思い出しても感謝しかありません。
東洋医学と看護に共通するもの
こうして妻から支えもあり、鍼灸の道を志したのですが、まず自分が鍼灸のどの分野に進むのかを考える必要がありました。
鍼灸の世界は、西洋医学に基づく鍼灸と東洋医学に基づく鍼灸の二つの領域に分かれていることは知っていため、そのどちらを選択するか最初に決定しなければなりませんでした。
当時からこの二つは理論も技術も異なっているため、同じ鍼灸の名を冠していても、もはや別物であると思っていたからです。
この点、健康な時間を長く過ごしてほしいという自分の想いにより近いのは「未病治」や「養生」といった思想がある東洋医学の方でした。
「未病治」とは、身体に不調を感じ始めた段階で治療を行うことで、病気への進行を防ぎ、健康な状態を維持していくという考えです。
「養生」とは、健康を維持し、病気を予防するためには、食事、運動、睡眠、ストレス対策などの日常生活の習慣を整えることが大切であるという考えです。
近年、「健康寿命」の重要性が訴えられていますが、東洋医学では数千年前からこのような思想があったことは驚くべきことだと思います。
一方、看護師は患者さんの意思を尊重しながら、病気の早期発見や生活習慣の改善を促すことで、健康を増進し、自立した生活を送れるように援助していくという役割を有しています。
このように、東洋医学と看護には「健康寿命」を促進し、生活習慣を整えていくという共通点があることがわかりました。
そのため、看護師としての臨床経験を生かしていくためにも西洋医学ではなく東洋医学に基づいた鍼灸を選択することとしました。
現代社会における鍼灸の役割
以上のような経緯から、東洋医学に基づく鍼灸の理論と技術を用いて、治療に当たっています。
日々の治療を通して、東洋医学ならびに鍼灸はストレス社会といわれる現代において非常に有効な治療方法であると確信するようになりました。
一般的にストレスを引き起こす要因は主に外的要因と内的要因に分かれます。
外的要因には、人間関係、仕事上のプレッシャー、経済的な要因、気候の変化などが含まれます。一方、内的要因には、緊張状態の継続、自己肯定感の低下、睡眠不足、不安感などが含まれます。
このような要因から生じるストレスの蓄積は心身に様々な変化を生じさせます。生活習慣を乱れさせ、自律神経のバランスが崩れることにより、不定愁訴が現れるようになります。
不定愁訴とは、検査では身体に明らかな異常が認められないが、様々な不調や不快感を訴える状態をいいます。
「不定愁訴の種類」
・頭痛、めまい
・肩こり、腰痛
・胃の不快感、下痢や便秘
・倦怠感、疲労感、息が浅い
・不眠、動悸、耳鳴り
・月経不順
・気分の落ち込み
・不安感、イライラ
・集中力や判断力の低下
このような不定愁訴の原因ともいえるストレスは現代の「万病の元」といえるでしょう。
鍼灸師としての臨床経験を重ねるなかで、鍼灸には身体にかかるストレス反応をとらえ、自律神経の乱れを調整し、不定愁訴を改善する力があることが明確になっていきました。
東洋医学の目的は、全身の気のバランスを調整することで、今ある症状を改善するだけでなく、自己治癒力を上げ、体質を改善し、病気になりにくい身体づくりを目指すことです。
そのような東洋医学に基づいた鍼灸の治療効果は、当然身体全体へ広がるため、複数の不定愁訴に対して同時にアプローチすることが出来るようになります。
「健康寿命」の促進と併せて、病院での治療は難しいとされる不定愁訴、その症状を改善していくことが現代社会における鍼灸の役割であるのではと考えています。
以上が、当院が東洋医学とそれに基づく鍼灸治療を選んだ理由となります。
長文となりましたが、ここまでご覧いただきありがとうございました。
それでは、次回もよろしくお願いします。