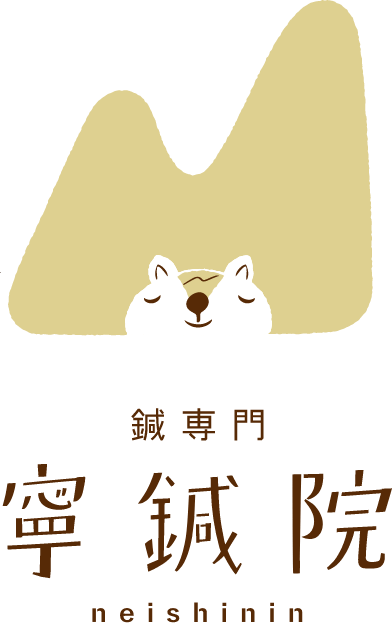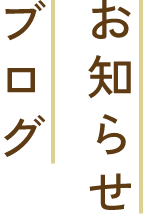2025.09.16
- ブログ
西洋医学による鍼灸と東洋医学による鍼灸
鍼灸業界以外の方にはあまり知られていないことですが、鍼灸の治療方法は大きく分けて二つのグループがあります。
一つは西洋医学(現代医学)に基づいた鍼灸、もう一つは東洋医学(古典医学)に基づいた鍼灸です。
大多数の鍼灸院は西洋医学による鍼灸を採用しており、鍼灸院の件数でいえば、東洋医学に基づく治療を行う鍼灸院は10件中1件にも満たないといわれています。
これは厚生労働省が西洋医学に基づく鍼灸を中心とした教育システムを採用しているため、臨床現場もその影響を受けているからです。
西洋医学(現代医学)に基づいた鍼灸は、その効果を鍼刺激から生じる神経伝達物質の促進による血流の改善や免疫反応の上昇によって生じるものと捉えています。
解剖学や生理学を理論の基礎として構築された治療方法であり、大学で研究されている電気鍼を中心とした鍼灸や1970年代に注目された「鍼麻酔」などもこのグループに属します。
東洋医学(古典医学)に基づいた鍼灸は、身体には「気」というエネルギーが流れているという概念を理論の根幹とし、鍼は気の流れを調整する道具として捉えています。
古代中国の思想から生まれた陰陽五行を基礎理論とし、一般的にツボといわれる経穴やその流れを示す経絡に対して鍼を行い、気の流れを整えることを治療目的としています。
漢方薬や薬膳はこのグループに属しており、当院の治療はこちら側になります。
この両者は基礎理論や技術体系などが大きく異なっており、もはや別ものであるといっても過言ではありません。
両者の最も大きな違いは「目に見えるもの」を重視するのか、「目に見えないもの」を重視するのかに現れていると個人的には考えています。
西洋医学は「目に見えるもの」を重視する医学です。レントゲン、CT、MRI、エコー検査、採血データなど人体の状態を誰もが視認できる画像や数字に表すことにより、患者やその家族と医療スタッフが現状に対しての認識を共有しすくなります。
基本的に受けられる医療の質が一定であり、複数のスタッフが関わることが安全性の確保にもつながっています。鍼灸の効果も客観的に評価できるため、効果を再現しやすいのが特徴となっています。
一方、東洋医学は「気」に代表される「目に見えないもの」を重視する医学です。脈診や腹診といった術者の五感を用いて、患者の身体の状態を把握し、気の流れの乱れを整えることを目標としています。
身体全体のバランスを調整出来ることから、自律神経失調症や現代医学では不定愁訴とされる症状の緩和には優れています。
しかし、その効果は術者の技量に左右されやすく、何より治療理論が古典を基礎としているため、馴染みのない現代人には理解しづらいことが難点となっています。
以上のように、鍼灸には西洋医学・東洋医学、二つのグループがあり、それぞれの特徴を考慮した上で、ご自身の症状に適した治療方法を行っている鍼灸院を選択していく必要があります。
ただし、コンビニの件数よりはるかに多いとされる鍼灸院・鍼灸整骨院からご自身に合った治療院を探し出すことは非常に困難であると推測されます。
そのため、このブログでは治療院を選ぶ際の参考にしていただければと考え、鍼灸に関連する様々な情報を発信しております。
今回のポイント
・鍼灸の治療は西洋医学(現代医学)と東洋医学(古典医学)の二つのグループに分かれている。
・両者の大きな違いは「目に見えるもの」「目に見えないもの」どちらを重視するかに現れている。
・西洋医学(現代医学)は客観的に評価しやすく再現性が高いが、東洋医学(古典医学)は理論がわかりづらく再現性が低い。
前述の通り、当院は東洋医学に基づいた理論と技術を用いて治療に当たっています。
看護師という西洋医学の臨床経験がありながら、なぜ、わかりづらく、再現性が低い東洋医学の方を選んだのか、次回は「当院が東洋医学に基づく鍼灸を選んだ理由」についてご説明させていただく予定です。
ここまでご覧いただきありがとうございました。
それでは、次回もよろしくお願いします。